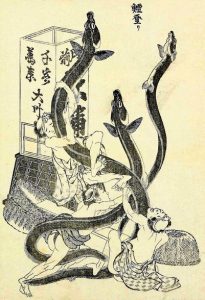スーパーや通販サイトで、数多く並んでいるうなぎの蒲焼。うなぎ蒲焼のパッケージを良くみると“●尾”と記載があります。今回はうなぎ蒲焼の大きさの説明、またどの大きさのうなぎ蒲焼がちょうど良いサイズなのかを、うなぎ博士に説明していただきます。

うなぎの“●尾”ってどのくらいの大きさ?
うなぎのサイズは60尾・70尾・80尾・・・などと表されます。スーパーのうなぎ蒲焼パッケージを見ると“70尾”など表示があります。うなぎのサイズは「10kgまでうなぎを入れられる箱」に何尾入るかを基準にして決められています。
例えば10kgあたり70尾と記載があれば、10kg仕入れたら70尾のうなぎが入っている、ということになります。

うな重にするのならどのくらいが良いの?

うなぎの場合、主に流通するサイズが10kgたり100尾 1尾あたり100g前後のものから大きいサイズで10kgあたり50尾 1尾あたり200g前後が主力になります。
関東に関しては言えば、昔からの流れで「1人前に対して1尾」という概念が非常に根強いため比較的小さめ10kgあたり70尾~100尾をよく使います。
関西になると「1人前に対して1尾」という習慣が比較的少ないため、お店に行くと、比較的大きめで肉厚で食べ応えのあるうなぎを使います。
うな重にしても1尾は食べきれないため、「1人前に対して1尾」ではなく、切り身にしたものが何切れ乗っているかで値段が変わります。
特に福岡の柳川地区などはもっと大きなサイズの10kgたり40尾(約250g)、もしくはそれ以上のサイズのうなぎをごはんの上にのせて、せいろで蒸しあげる“せいろ蒸し”という料理もあります。地域によって食文化が違う、使ううなぎの大きさも異なるというのがうなぎの特徴です。
うな重だと“並”“上”“特上”の違いはなに?

うな重だと“並”“上”“特上”などあって、ご飯に対するうなぎの量でランクが変わります。
うなぎの重量1に対してごはんの量が2となるような割合が適当です。うな重に盛り付けた時の最適なサイズは110-120gとなります。これを並とするお店が関東では多いです。70尾(140g前後)の場合、ごはんの量に対してうなぎの量が多く贅沢感がでる“上”“特上”に使われるサイズとなります。
つまり関東では、80尾(120g前後)と比較的小さめのうなぎサイズを好みます。
ご家庭では、ごはん200gの容器であれば、うなぎ半分でも十分なバランスになります。他におかずがあればうなぎを3つに切って3人で分けるなどすれば良いと思います。うなぎ1に対して、ごはん3のイメージでうなぎを選んでいただく比較的バランスの良いうな重(うな丼)になります。
関東と関西、うなぎ蒲焼の特徴は?
関東は柔らかく仕上げるのは多い地区です。いったん素焼きで白焼きした後に蒸しを入れ、よりふっくら柔らかにしたものにタレをつけて蒲焼きにします。蒸すことでうなぎから余分な脂が落ちるので、あっさりしたタレをうなぎに吸わせるように焼いていくのが関東風うなぎ蒲焼の調理法です。タレはあっさりめで比較的、醤油の味が引き立つようなタレになります。
関西風は蒸しを入れません。さらに捌き方も異なり、白焼きも強くは焼き込まない。わざと食感を残した形でタレをつけていきます。関東に比べるとうなぎに脂が残っているので、関東風のタレだとうなぎが油分でタレをはじいてしまいます。お店ごとにいろいろな工夫がありますが、トロみをつけるために砂糖を多めに入れて煮詰めたり、場合によってはわざとアルコールを残し煮切らないタレで焼いていく(焼けばアルコールは飛ぶ)などあります。脂に負けない強さをもったタレで焼いていきます。

蒲焼と違いが醤油の文化の違いもあると思います。九州は醤油に糖分がある甘い醤油が多い。そこにさらに甘みを加える。醤油の文化が異なるので、蒲焼のタレだけみても全国様々なものがある。関東から地方に行け行くほど味は濃くなっていく傾向です。
まとめ
うなぎのちょうど良いサイズはどのくらいだろう、と思われていた方も、だいぶ明確に選び方が分かるようになったのではないでしょうか?贅沢な美味しさなのに手軽にいただけるうなぎを是非ご家庭でも楽しんでみてくださいね!
美味しい冷凍うなぎは大五うなぎ工房にお任せ下さい。